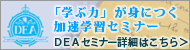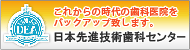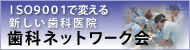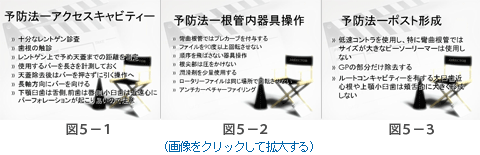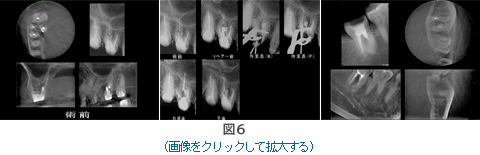基礎ができてこその治療の高度化
医療法人晴和会 うしくぼ歯科 牛窪 敏博 院長

牛窪敏博先生は、開業後にペンシルバニア大学歯内療法学教室大学院に留学し、キム教授の薫陶を受け、エンドドンティックレジデントプログラムを修了しました。キム教授は全米で最も有名な根管治療の専門医であり、アメリカで初めて歯内療法の分野にマイクロスコープ(手術用実体顕微鏡)を応用し、その臨床技術を全米に普及させたパイオニアとして知られています。帰国後、牛窪先生は早々にマイクロスコープにて臨床応用を始め、さらに「本当の根管治療」を提供するためにと、「ハイパー根管治療」専門のU’z大阪歯科医院を開設に至りました。昨今はインプラントが隆盛を極め、歯科医側も患者さん側も人工の歯に頼りがちです。しかしながら牛窪先生は「自分の歯を残すこと」にこだわり、「適切な根管治療を行えば、インプラント治療を希望する患者さんの約3割は自分の歯を残せる」との信念を持って治療にあたっています。
このコーナーでは、牛窪先生に世界最先端の根管治療についてご紹介して頂きます。

医療法人晴和会 うしくぼ歯科 牛窪 敏博 院長
プロフィール
- 1988年 朝日大学歯学部 卒業
- 1992年 うしくぼ歯科 開業
- 1998年 ペンシルバニア大学マイクロスコープエンドドンティクスコース 終了、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯髄生物学教室 入局
- 2001年 同大学専攻生 終了
- 2002年 日本歯内療法学会認定医取得 AAE会員
- 2003年 医療法人晴和会 うしくぼ歯科 理事長、ISO9001取得(2000年度版)
- 2005年 東京歯科大学歯内療法学講座
- 2006年 ペンシルバニア大学歯内療法学教室インターナショナルプログラムエンドドンティックレジデント
第5回:「根管治療中、パーフォレーションに遭遇したら?」 2009.2.1
日常の臨床で遭遇する機会の多い再根管治療は、もう既に起こっている様々な障害が治療の難易度を高めている。そこで今回、このような再根管治療のさまざまな問題の中の1つに挙げられるパーフォレーションについて考察し、根管治療のオプションとしてその修復法を取り入れて頂ければ、診療の幅が広がるばかりではなく、患者と共に歯牙保存の価値が共有できる
1.
定義と分類:パーフォレーションと言っても治療を開始する前から存在するものと、不幸にも術者自ら起こしてしまったものとの2つが考えられるが、どちらにしてみてもオリジナルの根管とは異なった所に穴があいてしまっていることには変わりなく、歯科医原的な傷害である。 1994年にAlhadainyは“パーフォレーションとは根管と歯周組織または口腔との間に人工的に形成された交通路である”と定義づけしている。
 分類としてはa:歯頸部三分の一、b:歯根中間部三分の一、c:根尖部三分の一の3つに分けられ、a:歯頸部三分の一では歯冠部、髄床 底部、根管口側方部の3種類に分けられる(図1)。
分類としてはa:歯頸部三分の一、b:歯根中間部三分の一、c:根尖部三分の一の3つに分けられ、a:歯頸部三分の一では歯冠部、髄床 底部、根管口側方部の3種類に分けられる(図1)。
また、歯冠部では歯肉縁上、歯肉縁上で尚かつ歯槽骨頂上、歯槽骨頂下に分類される。b:歯根中間部では大臼歯の根管内湾側に発生する、ストリップパーフォレーションと中間部における側法穿孔があり、c:根尖部では根尖孔の移動、根尖破壊、リッジに伴う穿孔が挙げられる。
2.
組織学的見解:パーフォレーションとは組織学的に見てみると、慢性的な炎症反応が常に存在し上皮性の肉芽組織が穿孔部に充満し、歯根膜は寸断されている状態にある。Beaversらは無菌的な状態で髄床底と側方部におけるパーフォレーションの動物実験を行った結果、3つの治癒段階が考えられると述べている。
先ず、第一段階(処置後2~7日)は、人工的穿孔が起こると早期に血餅、RBC、PMNSは歯根膜と壊死を起こしている穿孔部の周りに凝集し、受傷後4~7日で繊維芽細胞が穿孔部に向かって集まり始める。第二段階(処置後7~14日)では血餅は吸収され炎症性の細胞浸潤は減少し、肉芽化が進み繊維芽細胞は穿孔象牙質部表面に平行に整列する。第三段階(処置後14~21日)においては、低いレベルで炎症はあるものの、新しく組織化された歯根膜は隣接する正常な歯根膜によく似た繊維性に富んだ組織が観察される。そして、穿孔部象牙質に沿ってセメント様硬組織が沈着し、新生骨が穿孔部に沿って形成されていた。
3.
治療後の予後を左右する因子:予後を左右する因子として考えられるものとして、1996年Fuss & Trope は以下のような要因があると述べている。a) 時間 b) 大きさ c) 位置 d) アクセスの容易性 e) 修復材料 の5項目を挙げており、時間的要因に関しては出来る限り早期の処置が望ましく、遅れれば遅れるほど予後は悪くなる。骨破壊も進み、肉芽組織が根管内に多量に侵入し、その後の処置操作を困難にする。大きさに関しては小さい方が予後は良く、大きくなると組織のダメージも大きくなり止血が困難となり封鎖性に問題を生じる。位置的要因としては歯冠側1/3 中間部1/3 根尖部1/3に分けられる(図2)。
根尖部の穿孔は一見予後が悪いように思えるが、ダメージを受けた歯周組織及び歯根部が限られた範囲であり健全な残存歯根膜・歯根が多く残っている為、比較的この部位での予後は良い、また歯冠側になるに従い不良となる。
特に、分岐部での穿孔は予後が悪く骨吸収が進むだけでなく歯周ポケットと交通してしまうと加速的に崩壊する。アクセスに関しては、現在マイクロスコープにより十分な光量の下、拡大して観察、処置が可能であるが、部位によっては熟練が必要である。修復材料としてはマトリックスと主たる充填材とに分けて考える。これは1992年Lemonが提唱しているInternal Matrix Concept に基づいており、マトリックスとしての条件は止血効果があり、修復材料の過剰充填を防ぎ、上皮細胞の増殖を抑えることが出来る基盤となる等がある(図3)。
主たる充填材の特徴としてBallaらは、生体親和性、毒性がなく、骨及びセメント質に適しており、封鎖性が良い等を挙げている(図4)。中でもMTAは特に治療成績が良く、今のところ信頼できる材料と言えるであろう。ただし、操作性は悪く熟練する必要がある。
4.
原因と予防法:原因として考えられる項目はアクセス、根管内器具操作、ポスト形成が挙げられる。アクセスに関して歯冠部分の解剖を良く理解し特に歯冠歯根ともに長い歯牙や石灰化している根や近遠心根が非常に狭窄している場合、注意する必要がある。根管内器具操作は常に慎重に行う必要があり、特に臼歯ではアンチカーベチャーファイリングを意識しながら歯質の薄いエリアにおいて過剰切削しないように心がける。リッジやブロック等の障害を越えるがために不用意な器具操作を行った結果、穿孔を起こす場合もある。ポスト形成では高速回転のハンドピースの使用による謝った長軸方向への過剰切削と大きなスクリュウポストの選択がある。医原的穿孔の半分はこのポスト形成が原因しているとも言われている。(図5‐1、2、3)
5.
診断:穿孔であると診断を行う為にはいくつかの方法で診査する必要がある。アクセスキャビティー中での穿孔は恐らくミラーテクニックで直視可能であるが、それ以外ではマイクロスコープや歯科用コーンビームCTがあれば診断し易い筈である(図6)。また、デンタルレントゲン、手指感覚、根管長測定器、治療中の突然の出血、処置後の持続的な症状等が穿孔を確定する診査方法および診断の目安となる。
6.
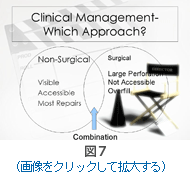 治療方法:具体的な治療法はa)非外科的修復法 b)外科的修復法 c)両者を組み合わせた方法 が挙げられる。(図7)
歯冠側1/3において、歯肉縁上では通常の5級窩洞修復に準じ、歯肉縁下・骨縁上ではフラップオペを行いそして修復し、歯肉縁上・骨縁下および中間部1/3でアクセス可能なストリップパーフォレーションは非外科的修復法を選択する。また、中間部1/3でアクセス不可能なストリップパーフォレーションやリペアー失敗症例は非外科的―外科的修復法の組み合わせを選択する。根尖部1/3では外科的修復が妥当である。
治療方法:具体的な治療法はa)非外科的修復法 b)外科的修復法 c)両者を組み合わせた方法 が挙げられる。(図7)
歯冠側1/3において、歯肉縁上では通常の5級窩洞修復に準じ、歯肉縁下・骨縁上ではフラップオペを行いそして修復し、歯肉縁上・骨縁下および中間部1/3でアクセス可能なストリップパーフォレーションは非外科的修復法を選択する。また、中間部1/3でアクセス不可能なストリップパーフォレーションやリペアー失敗症例は非外科的―外科的修復法の組み合わせを選択する。根尖部1/3では外科的修復が妥当である。
7.
その他の治療法:解剖学的な制約や根形態、器具到達性、予知性を考えるとルートアンプテーション、ヘミセクション、意図的再植、矯正的挺出そして抜歯という決断をせざるを得ないこともある。
8.
まとめ:あまり遭遇したくはないパーフォレーションであるが、その場合はパニックにならずに落ち着いて、早期に無菌的アプローチで的確な処置を最適な材料にて行い、予後調査をしていく必要がある。