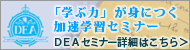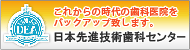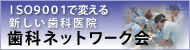基礎ができてこその治療の高度化
医療法人晴和会 うしくぼ歯科 牛窪 敏博 院長

牛窪敏博先生は、開業後にペンシルバニア大学歯内療法学教室大学院に留学し、キム教授の薫陶を受け、エンドドンティックレジデントプログラムを修了しました。キム教授は全米で最も有名な根管治療の専門医であり、アメリカで初めて歯内療法の分野にマイクロスコープ(手術用実体顕微鏡)を応用し、その臨床技術を全米に普及させたパイオニアとして知られています。帰国後、牛窪先生は早々にマイクロスコープにて臨床応用を始め、さらに「本当の根管治療」を提供するためにと、「ハイパー根管治療」専門のU’z大阪歯科医院を開設に至りました。昨今はインプラントが隆盛を極め、歯科医側も患者さん側も人工の歯に頼りがちです。しかしながら牛窪先生は「自分の歯を残すこと」にこだわり、「適切な根管治療を行えば、インプラント治療を希望する患者さんの約3割は自分の歯を残せる」との信念を持って治療にあたっています。
このコーナーでは、牛窪先生に世界最先端の根管治療についてご紹介して頂きます。

医療法人晴和会 うしくぼ歯科 牛窪 敏博 院長
プロフィール
- 1988年 朝日大学歯学部 卒業
- 1992年 うしくぼ歯科 開業
- 1998年 ペンシルバニア大学マイクロスコープエンドドンティクスコース 終了、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯髄生物学教室 入局
- 2001年 同大学専攻生 終了
- 2002年 日本歯内療法学会認定医取得 AAE会員
- 2003年 医療法人晴和会 うしくぼ歯科 理事長、ISO9001取得(2000年度版)
- 2005年 東京歯科大学歯内療法学講座
- 2006年 ペンシルバニア大学歯内療法学教室インターナショナルプログラムエンドドンティックレジデント
第6回:「パルプテスターの臨床での活用法」 2009.4.1
歯髄反応試験は歯髄の生死を診断する上で非常に重要な試験である。直接的には歯髄内の血流を計測(レーザードップラー血流計)することが必要であるが、実際にはコストや手間、そして測定誤差を受け易い等の器機そのものの開発に問題があり現実的ではない。そこで間接的な方法として冷/温熱刺激、電気的刺激が一般的である。しかし、あくまでも血流ではなく神経線維の興奮を見ているという点を忘れてはならない。また、電気歯髄診で注意しないといけないことは、外傷歯や根未完成歯、矯正治療中の歯牙には反応しない場合が多く、反応しないから歯髄は死んでいると誤って判断しないようにしなければならない。つまり、偽陽性反応と偽陰性反応を理解する必要がある。偽陽性反応とは、知覚反応はあるが失活歯髄のことであり、偽陰性反応とは、知覚反応はないが生活歯髄を意味する。また、Petersson et al 1986 によると、電気歯髄診の感度は88%で特異度は84%で温熱診によるものと比べるとその精度は高いとの報告がある。

実際の臨床ではパルプテスターの正しいルールに従った操作手順を守る必要があり、このルールを守らないと正確な情報が得られず誤った診断に繋がるのでよく注意する。
 先ず、
先ず、
① 対象となる歯牙をよく清掃し乾燥させる。
② ストリップスまたはラバーダムを用いて隣在歯より隔離する。
③ リップクリップ付アース用リードを口唇または口角に取り付ける。このとき患者さんにリップクリップを手で持ってもらっても構わない。
④ 媒介物処理(ペースト塗布)を行った後にパルプテスターのプローブ先端部を歯牙の切端にあてて計測を行う。
⑤ 計測は繰り返し数回行い、その数値が50以上の場合はその計測値は破棄する。つまり応答範囲の最高値は80であるが、この50~80の値は不安定要素を含むからである。
⑥ コントロールとして反対側同名歯を計測する。

ただ、歯髄診断においてセラミッククラウン等の全部被覆冠や、インレーやアマルガムの2級修復が施されている歯牙で隔離が出来ず隣在歯へ電流が漏洩する場合は正確な診断が出来ないことがある。このような場合は温度診を用いることになり、ドライアイス(マイナス78℃)を使用した方法が現在でも最も有効的で簡便な方法である。
電気歯髄診は信頼性の高い診断法であるが、間違った方法では正確な情報が得られず、誤診に繋がるので注意する必要がある。また、一つの方法だけで正確な診断が出来るという物はなく、電気歯髄診を中心にそれ以外の術式も併用し診断することが必要であり、またあくまでも神経の反応を見ているだけであり血流を見ているわけではないことを再確認して頂きたい。