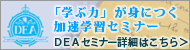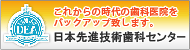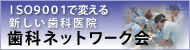基礎ができてこその治療の高度化
医療法人晴和会 うしくぼ歯科 牛窪 敏博 院長

牛窪敏博先生は、開業後にペンシルバニア大学歯内療法学教室大学院に留学し、キム教授の薫陶を受け、エンドドンティックレジデントプログラムを修了しました。キム教授は全米で最も有名な根管治療の専門医であり、アメリカで初めて歯内療法の分野にマイクロスコープ(手術用実体顕微鏡)を応用し、その臨床技術を全米に普及させたパイオニアとして知られています。帰国後、牛窪先生は早々にマイクロスコープにて臨床応用を始め、さらに「本当の根管治療」を提供するためにと、「ハイパー根管治療」専門のU’z大阪歯科医院を開設に至りました。昨今はインプラントが隆盛を極め、歯科医側も患者さん側も人工の歯に頼りがちです。しかしながら牛窪先生は「自分の歯を残すこと」にこだわり、「適切な根管治療を行えば、インプラント治療を希望する患者さんの約3割は自分の歯を残せる」との信念を持って治療にあたっています。
このコーナーでは、牛窪先生に世界最先端の根管治療についてご紹介して頂きます。

医療法人晴和会 うしくぼ歯科 牛窪 敏博 院長
プロフィール
- 1988年 朝日大学歯学部 卒業
- 1992年 うしくぼ歯科 開業
- 1998年 ペンシルバニア大学マイクロスコープエンドドンティクスコース 終了、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯髄生物学教室 入局
- 2001年 同大学専攻生 終了
- 2002年 日本歯内療法学会認定医取得 AAE会員
- 2003年 医療法人晴和会 うしくぼ歯科 理事長、ISO9001取得(2000年度版)
- 2005年 東京歯科大学歯内療法学講座
- 2006年 ペンシルバニア大学歯内療法学教室インターナショナルプログラムエンドドンティックレジデント
第8回:「これからの歯科医院形態について」 2009.8.1
21世紀に突入してからも日本の歯科業界はまだまだ冬の時代で、明るいニュースはあまり無い。ただインプラントに関しては現在、90年代初頭日本経済のバブル時代のごとくインプラントバブルと言わざるを得ない感がある。猫もしゃくしもインプラントで、特に若い先生はインプラント治療を目標に研鑽をし、あたかもこのインプラントが出来る歯科医師が優秀でお金持ちになる唯一の道であると信じている先生もいるぐらいである。いやはや困った問題である。
インプラント治療そのものはすばらしい治療であるが、その選択基準や適応症を間違えて判断してしまう場合があると聞く。一人で臨床を行っていくと相談できる先輩や同僚の歯科医師がいれば良いが、もしいなければ判断を間違えてしまう場合もあるであろう。勤務医時代はそのような状況でなくても、いざ独立開業してみると一国一城の主である以上、すべての診療に関する診査診断、治療責任は院長にかかってくる。たとえスタディーグループに所属していたとしてもそうそう頻繁に相談も出来ないであろう。また同じGPとしての視点でしか見られない場合が多いと思われる。
そこで我々が提唱するグループプラクティスが必要となってくる。インターディシプリナリーアプローチという言葉が日本に入ってきて以来35年以上経つと言われているなか、都市部の一部の先生の間でのみ、このようなシステムで診療を行っている程度である。
離ればなれの所に点在する専門に特化した歯科医院に患者さんは行ったり来たりする必要がある。最初は患者さんもおそらく我慢して通院して頂けるが、その頻度が増えるとやはり徐々に疲れが出てき始め、ギブアップする方や不満を漏らす方もチラホラ現れる。そうなると段々遠のき、やはり自分で全ての治療を行う方がストレス無く行えると考えるようになるのが自然の性である。これではいくらこのすばらしい仕組みを推奨しても広まる筈が無い。
日本独特の保険診療をベースに行われている歯科治療は良い部分もあるが悪い部分もある。歯科治療は狭い範囲であるから一人で全部出来る筈であると考える歯科医も多いであろう。それが出来る先生は良いが、やはり人間、得手不得手があり、得意分野と不得意分野があるのも事実であろう。そうなると一カ所で、ある程度の専門性が発揮できるシステムが必要である。それが、グループプラクティスである。
テナントビルの場合は同じフロアーまたは各フロアー間での専門性を生かした独立採算制を前提とした複数の歯科医院の開業プラン、一戸建ての場合では各専門歯科医師の共同出資による医院運営で売り上げ比率に係数を加味した算出方法で利益を分配する形態をとるプラン等いろいろ考えられる。また、一つの医院に勤務医として専門性を生かして治療を担当していくことも考えられる。これからは開業せずに何らかの形で歯科医院に永久就職する先生も出てくるであろう。
我々はビル開業で2階がGP兼審美歯科補綴専門のクリニック、3階がマウスピース矯正(インビザライン)専門のクリニック、4階が筆者の根管治療専門のクリニックである。各クリニックに直接来られる患者さんもいれば他のクリニックからのご紹介の患者さん、そして各フロアーのクリニックからのご紹介の患者さん、これら全ての患者さんの治療に関して、違う専門分野のドクターの視点でのアドバイスや提案がいつ何時でもディスカッションが可能なのである。同じ視点ではなく違う視点での意見交換は大変有効的で刺激的である。常にこのような関係が構築できるということは患者さんにもアピールが十分行うことができ、また実際に共同で行った臨床例も提示でき、我々が考える最良の治療を患者さんとともに共有できモチベーション向上にも繋がる。
このように、これからは一人での独立開業よりも複数の歯科医によるグループプラクティス形態が歯科医師と患者さん双方が納得のいく歯科治療を実現できるソリューションになるではないかと考えている。
(全て同じデザイナーによる:Tap Planning)